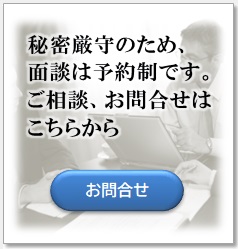黒字化一転、倒産寸前
経営コンサルタントコラム
2016年10月25日
経理が先月の試算表を持ってきました。
(経理)「社長、先月の試算表が出来ました。先月は黒字です。」
経理が言うに会社は黒字だそう。
(社長)「そうか、ご苦労さん。黒字化か、よくやった。」
(経理)「原価率も削減できました。」
(社長)「原価も下がったか、努力の成果が出たな。」
社長さんは、「先々月の赤字改善を指示した効果が出たな、よしよし。黒字なら問題ないぞ。原価率も改善したようだし、ひと安心だな」と満足げです。
黒字の内容をしっかり確認せず、上がってきた試算表をロクに見ないで、しまってしまいました。
しかしこの後、この社長さんは会社が倒産するかしないかの瀬戸際に立たされることになります。黒字化できていたのに。原価率も改善したのに。
一体なぜなのでしょう?
普通、黒字とか赤字とかいいますと、損益上の話になります。
営業利益で黒字とか、経常利益で黒字、税後で黒字とか。
事業成果という意味では、損益の数字が判断資料となります。
先月はいくら「利益」が出たか、という観点ですね。
赤字より黒字の方が良いですよね?と問われれば、ほぼ皆さん全員イエス、と答えられるでしょうし、確かにその通りです。
しかし、先の社長さんは黒字なのに倒産しそうになりました。
ということは、あながちそう(黒字であればOK)とも言い切れない、ということはピンときますね。
一方、開発型のベンチャー企業などで赤字を流し続けているのに倒産していない会社もあります。
製薬系のバイオベンチャーなどは毎年ウン十億とかいう赤字です。
で、なぜだ、という話。
結論から言うと、
お金を持ってればいくら赤字でも潰れない、
お金が無ければ黒字でも潰れる、
ということです。
さて、先述の黒字で喜んでいた社長さんの会社は、なぜ倒産の危機に陥ってしまったのでしょうか。
流れを見ていきましょう。
赤字に陥った先々月の損益状況を見ると、
売上高 100
粗利 15
販管費 20
営業損失 -5
経常損失-10
営業利益、経常利益ともに赤字。
粗利率が15%なので、原価率は85%。
で、黒字化した先月。
売上高 90
粗利 30
販管費 20
営業利益 10
経常利益 5
営業利益、経常利益ともに黒字。
粗利率が33%なので原価率は67%。
すごーく改善しているように見えませんか?
でも売上は若干落ちてるんですよね。
粗利が倍に増えているのが改善(のように見える)の要因。
でもなんか変ではないですか?
一気に粗利が倍になるなんて、おかしいですよね?
そうです、おかしいんです。
ここで粗利とは何だ、という知識が必要になります。
粗利とは売上から売上原価を引いたものです。
[粗利=売上-売上原価]
売上原価とは、もってた在庫に仕入を足して、残った在庫を引いたものです。
[売上原価=月初在庫+当月仕入-月末在庫]
売上が増えないのに粗利が増えたとすれば、売上原価が減少した、ということになります。
さて、売上原価が減少する要因は何でしょう。
月初の在庫と当月仕入、月末在庫すべて減少すれば、原価も当然減少しますが、そのほかにも原価を減少させる要因がありますね。
・月初の在庫と当月の仕入額を足したものが減る
・月末の在庫が増える
この2点ですね。
赤字だった先々月の売上原価の中身を見てみると、
月初在庫 30
+当月仕入 85
-月末在庫 30
―――――――――
売上原価 85(対売上高85%)
とこんな感じとなっています。
で、黒字の先月はというと、
月初在庫 30
+当月仕入 85
-月末在庫 55
―――――――――
売上原価 60(対売上高67%)
こちらに解説を加えるとこんな感じ。
月初在庫 30 ←先々月末の在庫とイコール
+当月仕入 85 ←先々月と同じ仕入高
-月末在庫 55 ←在庫増えてない!?
―――――――――
売上原価 60(対売上高67%)←在庫増えただけじゃん!
今回は月末の在庫が増えた、というのが原価率低減の理由だったんですね。
実は何も改善してなかったと。損益上利益は増えましたけど。
増えた在庫により、計算上原価が減少しただけの数字のマジックです。
とはいえ、増えた在庫は翌月に月初在庫となるわけで、トータルで言えばいったこい。
今月の原価がドーンと上がるだけで平均すれば同じ。
ならしてみれば特にどうこういう問題でもないです。残った在庫が確実に売れるのであれば。
ではお金的にはどうなってるか。
先々月最初の手持ち資金は45で、前月の売上が当月に入金されるとします。前月の売上は100でしたので、繰越分を入れて145が使えるお金です。
で、出ていく方を見ますと、
仕入額 85
+販管費 20
+借入返済 10(借入600を5年返済の月額)
―――――――――
支出 115
となります。
残ってたお金と入ってきたお金から出てったお金を引くと、
繰越分 45
+入金分 100
-支出額 115
―――――――――
残金 30
先々月は15のマイナスで残金は30となりました。
このままの状態で2カ月たつとお金が底をつきます。
でもこの段階で手を打てれば倒産は避けられますね。
そして何も手を打てず先月。
出ていく方は変わらず115です。
繰越分は30に減りました。
先々月の売上は100だったので、
繰越分 30
+入金分 100
-支出額 115
―――――――――
残金 15
支出変わらずの入金減少で残金が15まで落ちました。
ぎりぎり首の皮一枚で何とか資金ショートを回避したものの、すぐにでも手を打たないと資金ショート発生です。
損益上は粗利が倍増して黒字化した先月でしたが、現金収支上は倒産が迫ることになってしまいました。
本来であればここで急ぎ資金手当てなり、支出の調整をしないといけない局面です。
で、今月。
厳しい景況下、奮闘するも売上は100を回復するのが精一杯。
しかし前月仕入れた在庫は市場にマッチせず、不良化。
損益的には、
売上高 100
月初在庫 55
当月仕入 85
月末在庫 30
売上原価 110
粗利 -10
販管費 20
営業損失 -30
経常損失 -35
粗利でマイナスという、本来あってはならない状況となりました。
現金収支的には、収入面では先月売上分の90、支出は変わらず115。
繰越分 15
+入金分 90
-支出額 115
―――――――――
残金 -10
資金ショートです。
販管費の半分を払わないか銀行返済をやめるかしないとお金が足りません。
事態が判明後すぐに銀行さんに融資相談に行きましたが、間に合わず。
遊休不動産を担保にノンバンクから資金を30、融通してもらい、当面の事なきを得ました。
繰越分 15
+入金分 90
-支出額 115
―――――――――
残金 -10
+借入 30
―――――――――
残金 20
しかし今のままでは、また資金ショートに陥りますので、売上増加はもちろん、コスト削減努力をしないといけません。
収支は、返済猶予と役員報酬を未払いにして支出を減少させます。
繰越分 なし
+入金分 100 ←今月の売上
-支出額 100 ←借入返済10を猶予、役員報酬5を0に
―――――――――
残金 0
これでなんとかトントン。
こうしている間に販管費の圧縮、計画的な仕入等改善を図り、収支がプラスになるようにしなければなりません。
まさに再建の局面に入ってくることになります。
黒字回復!と喜んだのにこの状態。
売上とか原価とか利益とか、損益上の数値がある一方、上記のように「いくらお金が儲かった」か、という現金収支の観点もあるわけです。
カタカナで言えばキャッシュフローですね。
つまりは、現金がいくら増えたか減ったか、残ったか、という見方です。
会社を倒産させないためには、こちらの観点で経営を捉える必要があります。
極端に言えば、黒字であろうとなかろうと、お金が増えていればOK。
というのも、会社が倒産する、潰れるというのは、直接的には「お金」が無くなるからなんですね。赤字だから倒産するわけではないのです。
お金が無くなると給料も払えないし、家賃も払えない。物を作るための材料も仕入られないし、買掛けの支払もできなくなる。事業が成り立たなくなり、事業停止状態に陥ります。これが「潰れた」状態。
お金を借りても、お金は増えます。借りてくるんですから当然ですよね。
なので足りなければ借りる、という手段もあります。
銀行さんが貸してくれるのであれば。
しかし、実際のところ、本当にお金が必要になってから(つまりは資金不足が明らかになり、てんやわんやの状態)からでは、銀行は貸してくれません。
そもそも銀行の融資は最低でも1~2カ月の審査期間が必要ですし、晴れの日に傘を貸し、雨の日には傘を貸さないのが銀行です。
となると、他に資金不足を解消する手段がないと会社は、残念ながら突然に潰れます。
ですが、早め早めに情報を収集し、問題をきちんと把握しておけば、何がしかの手立てを打ち、倒産を回避したり、ソフトランディングすることもできます。
現金収支に注目し、戦略を考えていきましょう。
池田
 会社の「幸せな」たたみ方支援プロジェクト
廃業・事業承継のご相談を承ります。
弁護士・税理士・コンサルタントがチームで対応。
会社の「幸せな」たたみ方支援プロジェクト
廃業・事業承継のご相談を承ります。
弁護士・税理士・コンサルタントがチームで対応。